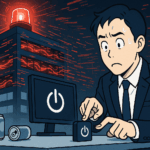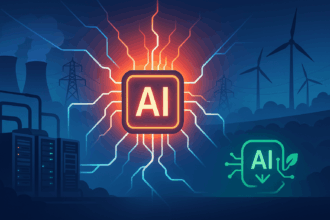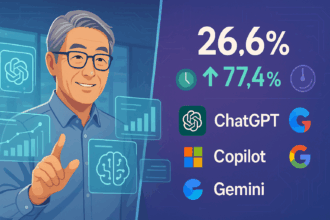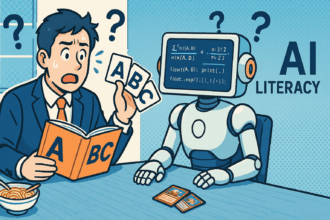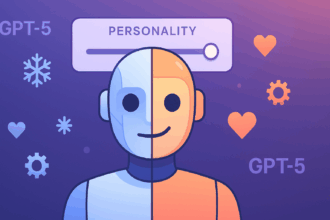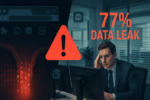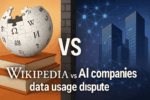記事まとめ
- AIの「ワールドモデル」とは、システムが内部に持つ環境の簡略化された表現である – まるで計算機版の雪の結晶玉のように、AIが現実世界の小型模型を頭の中に保持し、実際の行動前に予測や判断を評価できる仕組みだ。
- 1943年に心理学者ケネス・クレイクが提唱した古いアイデアが、現在のAI研究で再び脚光を浴びている – 初期のAI研究で挫折したこの概念が、深層学習の発展により再評価され、Meta、Google DeepMind、OpenAIなどの大手AI研究所が積極的に研究を進めている。
- 現在のLLMは真のワールドモデルではなく「ヒューリスティックの寄せ集め」を学習している – ChatGPTなどの生成AIは一貫した世界理解ではなく、バラバラな経験則の集合体で動作しており、これが幻覚や推論の不安定さの原因となっている。
対談: ワールドモデルって何?雪の結晶玉?
 松永尚人: 今回の記事は、AI研究で注目されている「ワールドモデル」について解説されていますね。簡単に言うと、AIシステムが内部に持つ環境の簡略化された表現のことで、現実世界の小型模型みたいなものを頭の中に持って、実際に行動する前に予測や判断を評価できる仕組みのことです。
松永尚人: 今回の記事は、AI研究で注目されている「ワールドモデル」について解説されていますね。簡単に言うと、AIシステムが内部に持つ環境の簡略化された表現のことで、現実世界の小型模型みたいなものを頭の中に持って、実際に行動する前に予測や判断を評価できる仕組みのことです。
 助飛羅知是: ワールドモデル!つまりAIが地球儀を持ってるってことですね!しかも雪の結晶玉みたいなやつ!これはもうSalesforceのTrailheadで学習パスを作るときの仕組みと同じかもしれませんね。ユーザーが迷子にならないように、全体のマップを最初に見せてあげるみたいな。
助飛羅知是: ワールドモデル!つまりAIが地球儀を持ってるってことですね!しかも雪の結晶玉みたいなやつ!これはもうSalesforceのTrailheadで学習パスを作るときの仕組みと同じかもしれませんね。ユーザーが迷子にならないように、全体のマップを最初に見せてあげるみたいな。
 松永尚人: まあ、比喩としては面白いですが、地球儀ではないですよ。記事によると、1943年に心理学者のケネス・クレイクが提唱した古いアイデアなんです。人間も頭の中に世界の小さなモデルを持っていて、それを使って「電車の前に飛び出したらどうなるか」を実験せずに予測できるという考え方です。
松永尚人: まあ、比喩としては面白いですが、地球儀ではないですよ。記事によると、1943年に心理学者のケネス・クレイクが提唱した古いアイデアなんです。人間も頭の中に世界の小さなモデルを持っていて、それを使って「電車の前に飛び出したらどうなるか」を実験せずに予測できるという考え方です。
 助飛羅知是: ああ、なるほど!つまりAIが頭の中でシミュレーションゲームをやってるってことですね!これって、Salesforceのフローで条件分岐を作るときに似てるかもしれません。「もしこの条件なら」「そうでなければ」って感じで、実際に実行する前に頭の中で流れを確認するみたいな。
助飛羅知是: ああ、なるほど!つまりAIが頭の中でシミュレーションゲームをやってるってことですね!これって、Salesforceのフローで条件分岐を作るときに似てるかもしれません。「もしこの条件なら」「そうでなければ」って感じで、実際に実行する前に頭の中で流れを確認するみたいな。
 松永尚人: それは悪くない例えですね。実際、初期のAI研究ではSHRDLUというシステムが「ブロックワールド」という簡単な世界モデルを使って、机の上の物体について常識的な質問に答えることができていたんです。でも複雑な現実には対応できなくて、一度は諦められたアイデアだったんです。
松永尚人: それは悪くない例えですね。実際、初期のAI研究ではSHRDLUというシステムが「ブロックワールド」という簡単な世界モデルを使って、机の上の物体について常識的な質問に答えることができていたんです。でも複雑な現実には対応できなくて、一度は諦められたアイデアだったんです。
 助飛羅知是: ブロックワールド!レゴの世界みたいですね!でもそれが諦められたって、なんでまた復活したんでしょうか?ギャハ!まさかAIがノスタルジーを感じるようになったとか?
助飛羅知是: ブロックワールド!レゴの世界みたいですね!でもそれが諦められたって、なんでまた復活したんでしょうか?ギャハ!まさかAIがノスタルジーを感じるようになったとか?
対談: ChatGPTは象を理解していない?盲人と象の寓話
 松永尚人: 復活した理由は深層学習の発展なんです。手作りのルールではなく、試行錯誤を通じて内部表現を構築できるようになったからです。でも興味深いのは、ChatGPTのようなLLMが実際には真のワールドモデルを持っていないということです。記事では「盲人と象の寓話」で説明されています。
松永尚人: 復活した理由は深層学習の発展なんです。手作りのルールではなく、試行錯誤を通じて内部表現を構築できるようになったからです。でも興味深いのは、ChatGPTのようなLLMが実際には真のワールドモデルを持っていないということです。記事では「盲人と象の寓話」で説明されています。
 助飛羅知是:「盲人と象の寓話」!知ってます!一人は鼻を触って「蛇みたい」、別の人は足を触って「木みたい」、尻尾を触った人は「ロープみたい」って言うやつですね!つまりChatGPTは象全体を理解せずに、部分部分でバラバラに覚えているってことでしょうか。
助飛羅知是:「盲人と象の寓話」!知ってます!一人は鼻を触って「蛇みたい」、別の人は足を触って「木みたい」、尻尾を触った人は「ロープみたい」って言うやつですね!つまりChatGPTは象全体を理解せずに、部分部分でバラバラに覚えているってことでしょうか。
 松永尚人: まさにその通りです!LLMは「ヒューリスティックの寄せ集め」、つまりバラバラな経験則の集合体を学習していて、一貫した全体像は持っていないんです。だから時々矛盾したことを言ったり、ハルシネーションを起こしたりするわけです。
松永尚人: まさにその通りです!LLMは「ヒューリスティックの寄せ集め」、つまりバラバラな経験則の集合体を学習していて、一貫した全体像は持っていないんです。だから時々矛盾したことを言ったり、ハルシネーションを起こしたりするわけです。
 助飛羅知是: なるほど!これってSalesforceのデータ管理でも同じことが起こりそうですね。顧客情報があちこちのオブジェクトに散らばっていて、統合された顧客像が見えないみたいな。だからData Cloudで統合する必要があるわけですね!
助飛羅知是: なるほど!これってSalesforceのデータ管理でも同じことが起こりそうですね。顧客情報があちこちのオブジェクトに散らばっていて、統合された顧客像が見えないみたいな。だからData Cloudで統合する必要があるわけですね!
 松永尚人: それは実は良い例えかもしれません。記事では、マンハッタンの道案内ができるLLMが、1%の道路をランダムに封鎖しただけでパフォーマンスが大幅に悪化した例が紹介されています。統合された地図があれば迂回ルートを見つけられるはずなのに、部分的な情報の寄せ集めだから対応できなかったんです。
松永尚人: それは実は良い例えかもしれません。記事では、マンハッタンの道案内ができるLLMが、1%の道路をランダムに封鎖しただけでパフォーマンスが大幅に悪化した例が紹介されています。統合された地図があれば迂回ルートを見つけられるはずなのに、部分的な情報の寄せ集めだから対応できなかったんです。
 助飛羅知是: ああ!つまりAIはGoogle Mapsを持ってないってことですね!部分部分の道は知ってるけど、全体の地図がないから、工事で道が使えなくなったら迷子になっちゃうと。これは困りますね。
助飛羅知是: ああ!つまりAIはGoogle Mapsを持ってないってことですね!部分部分の道は知ってるけど、全体の地図がないから、工事で道が使えなくなったら迷子になっちゃうと。これは困りますね。
 松永尚人: まさにそれが問題なんです。だからこそMeta、Google DeepMind、OpenAIなどの大手研究所がワールドモデルの開発に力を入れているわけです。真のワールドモデルがあれば、幻覚の削減、信頼性のある推論、システムの解釈性向上などが期待できるんです。
松永尚人: まさにそれが問題なんです。だからこそMeta、Google DeepMind、OpenAIなどの大手研究所がワールドモデルの開発に力を入れているわけです。真のワールドモデルがあれば、幻覚の削減、信頼性のある推論、システムの解釈性向上などが期待できるんです。
 助飛羅知是: でも、どうやって象の全体像を教えるんでしょうか?AIに象を触らせる?それとも象の写真を見せるんでしょうか?
助飛羅知是: でも、どうやって象の全体像を教えるんでしょうか?AIに象を触らせる?それとも象の写真を見せるんでしょうか?
 松永尚人: 実はそれが現在の大きな課題なんです。各社が異なるアプローチを試していて、まだ正解は見つかっていないというのが現状です。
松永尚人: 実はそれが現在の大きな課題なんです。各社が異なるアプローチを試していて、まだ正解は見つかっていないというのが現状です。
対談: AI各社の挑戦とワールドモデルの未来
 松永尚人: 記事によると、Google DeepMindとOpenAIは「マルチモーダル」なトレーニングデータ、つまり動画や3Dシミュレーション、テキスト以外の入力を大量に与えることで、ニューラルネットワーク内にワールドモデルが自然に形成されることを期待しているようです。一方、MetaのヤンLeCunは全く新しいAIアーキテクチャが必要だと考えているみたいですね。
松永尚人: 記事によると、Google DeepMindとOpenAIは「マルチモーダル」なトレーニングデータ、つまり動画や3Dシミュレーション、テキスト以外の入力を大量に与えることで、ニューラルネットワーク内にワールドモデルが自然に形成されることを期待しているようです。一方、MetaのヤンLeCunは全く新しいAIアーキテクチャが必要だと考えているみたいですね。
 助飛羅知是: マルチモーダル!つまりAIに五感を与えるってことですね!視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚…あ、でもコンピューターに味覚はどうやって教えるんでしょうか?ラーメン二郎の美味しさをAIに理解してもらいたいんですが。
助飛羅知是: マルチモーダル!つまりAIに五感を与えるってことですね!視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚…あ、でもコンピューターに味覚はどうやって教えるんでしょうか?ラーメン二郎の美味しさをAIに理解してもらいたいんですが。
 松永尚人: それは…まあ、将来的には化学センサーなどを使って可能になるかもしれませんが、今の話とは少しずれますね。重要なのは、各社が異なる方向でワールドモデルの実現を目指しているということです。これはSalesforceのAI戦略とも関連していて、Einstein GPTも様々なデータソースを統合してより良い予測や提案を行おうとしています。
松永尚人: それは…まあ、将来的には化学センサーなどを使って可能になるかもしれませんが、今の話とは少しずれますね。重要なのは、各社が異なる方向でワールドモデルの実現を目指しているということです。これはSalesforceのAI戦略とも関連していて、Einstein GPTも様々なデータソースを統合してより良い予測や提案を行おうとしています。
 助飛羅知是: そうそう!Einstein GPT!これもワールドモデルの一種と考えることができるかもしれませんね。顧客の行動、販売データ、マーケティング活動など、すべての情報を統合して「顧客の世界」を理解しようとしているわけですから。
助飛羅知是: そうそう!Einstein GPT!これもワールドモデルの一種と考えることができるかもしれませんね。顧客の行動、販売データ、マーケティング活動など、すべての情報を統合して「顧客の世界」を理解しようとしているわけですから。
 松永尚人: それは興味深い視点ですね。確かにCRMシステムは企業の「顧客ワールドモデル」と言えるかもしれません。顧客の過去の行動から将来の行動を予測し、最適なアプローチを決定する…まさにワールドモデルの考え方と同じです。
松永尚人: それは興味深い視点ですね。確かにCRMシステムは企業の「顧客ワールドモデル」と言えるかもしれません。顧客の過去の行動から将来の行動を予測し、最適なアプローチを決定する…まさにワールドモデルの考え方と同じです。
 助飛羅知是: でも記事を読んでいて気になったのは、ワールドモデルの「検証可能性」の話です。AIが本当に世界を理解しているのか、それとも上手に真似しているだけなのか、どうやって判断するんでしょうか?
助飛羅知是: でも記事を読んでいて気になったのは、ワールドモデルの「検証可能性」の話です。AIが本当に世界を理解しているのか、それとも上手に真似しているだけなのか、どうやって判断するんでしょうか?
 松永尚人: それが現在の大きな課題の一つです。記事では「堅牢で検証可能なワールドモデル」の重要性が指摘されています。単に正しい答えを出すだけでなく、なぜその答えに至ったのかが説明できることが重要なんです。これはAIの信頼性に直結する問題ですね。
松永尚人: それが現在の大きな課題の一つです。記事では「堅牢で検証可能なワールドモデル」の重要性が指摘されています。単に正しい答えを出すだけでなく、なぜその答えに至ったのかが説明できることが重要なんです。これはAIの信頼性に直結する問題ですね。
 助飛羅知是: なるほど!つまりAIに「なんで?」って聞いたときに、ちゃんと理由を説明できることが大切なんですね。子供みたいに「なんでなんで」攻撃をしても答えられるAIを作ろうってことでしょうか。
助飛羅知是: なるほど!つまりAIに「なんで?」って聞いたときに、ちゃんと理由を説明できることが大切なんですね。子供みたいに「なんでなんで」攻撃をしても答えられるAIを作ろうってことでしょうか。
 松永尚人: まあ、そう言えなくもないですね。実際、説明可能AIの研究は重要な分野です。特に企業で使う場合、AIの判断根拠が分からないと、重要な意思決定に使うのは危険ですから。
松永尚人: まあ、そう言えなくもないですね。実際、説明可能AIの研究は重要な分野です。特に企業で使う場合、AIの判断根拠が分からないと、重要な意思決定に使うのは危険ですから。
 助飛羅知是: そういえば、ワールドモデルができたら、AIがMagic: The Gatheringで僕に勝てるようになるんでしょうか?現在のAIはルールは知ってるけど、戦略的な思考とか、相手の心理を読むとかは苦手そうですよね。でもワールドモデルがあれば、「このカードを出したら相手はこう反応するだろう」みたいな予測ができるようになって…ギャハ!これは大変だ!
助飛羅知是: そういえば、ワールドモデルができたら、AIがMagic: The Gatheringで僕に勝てるようになるんでしょうか?現在のAIはルールは知ってるけど、戦略的な思考とか、相手の心理を読むとかは苦手そうですよね。でもワールドモデルがあれば、「このカードを出したら相手はこう反応するだろう」みたいな予測ができるようになって…ギャハ!これは大変だ!
 松永尚人: え?!それはちょっと飛躍しすぎでしょ!でも確かに、真のワールドモデルができれば、AIの能力は格段に向上するはずです。ただ、まだまだ研究段階で、実用化には時間がかかりそうです。むしろ今は、SalesforceのようなCRMシステムでデータを統合して、お客様の「ワールドモデル」を構築することの方が現実的かもしれませんね。もしAIについてもっと詳しく知りたい方がいらしたら、ぜひ弊社にご相談ください!
松永尚人: え?!それはちょっと飛躍しすぎでしょ!でも確かに、真のワールドモデルができれば、AIの能力は格段に向上するはずです。ただ、まだまだ研究段階で、実用化には時間がかかりそうです。むしろ今は、SalesforceのようなCRMシステムでデータを統合して、お客様の「ワールドモデル」を構築することの方が現実的かもしれませんね。もしAIについてもっと詳しく知りたい方がいらしたら、ぜひ弊社にご相談ください!
関連リンク
元記事: ‘World Models,’ an Old Idea in AI, Mount a Comeback – Quanta Magazine